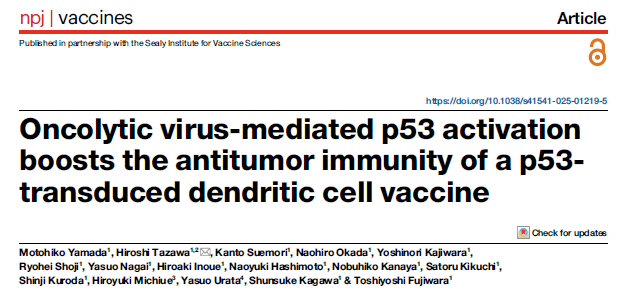こんにちは、シエン(@M12n08Jp)です。
オンコリスのウイルス療法がNatureに掲載されました。
論文ページ(原文:英語)→ https://www.nature.com/articles/s41541-025-01219-5
以下、邦訳です。
ウイルス療法によるp53活性化は、p53遺伝子導入樹状細胞ワクチンの抗腫瘍免疫を増強する
Motohiko Yamada¹, Hiroshi Tazawa¹ ², Kanto Suemori¹, Naohiro Okada¹, Yoshinori Kajiwara¹,
Ryohei Shoji¹, Yasuo Nagai¹, Hiroaki Inoue¹, Naoyuki Hashimoto¹, Nobuhiko Kanaya¹,
Satoru Kikuchi¹, Shinji Kuroda¹, Hiroyuki Michiue³, Yasuo Urata⁴, Shunsuke Kagawa¹, Toshiyoshi Fujiwara¹
-
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 消化器外科学分野
-
岡山大学病院 革新的臨床医学センター
-
岡山大学病院 中性子治療研究センター
-
オンコリスバイオファーマ株式会社
概要
複製欠損型のヒト野生型p53遺伝子を発現するアデノウイルス(Ad-p53)を用いて遺伝子導入した樹状細胞(Ad-p53 DCs)は、p53を標的とした細胞傷害性T細胞(CTL)を誘導します。しかしながら、腫瘍細胞におけるp53の免疫原性の低さと免疫応答の弱さにより、Ad-p53 DCsの抗腫瘍効果は限定的です。
そこで、我々は腫瘍特異的にp53を発現させ、抗腫瘍免疫を誘導するためのp53導入型腫瘍溶解性アデノウイルス「OBP-702」を開発しました。本研究では、Ad-p53 DCsとOBP-702の併用効果をマウスの大腸がん(CT26およびMC38)モデルを用いて検討しました。
CT26(p53野生型)およびMC38(p53変異型)の皮下腫瘍モデルにおいて、Ad-p53 DCsとOBP-702の併用治療は、治療部位および非治療部位の両方で腫瘍成長を有意に抑制しました。これはCD8+ CTLsおよびCD11c+ DCsの腫瘍浸潤の増加によるもので、OBP-702に感染した腫瘍細胞は、MHC分子の文脈でヒトp53エピトープを提示し、Ad-p53 DCsにより誘導されたCTLによって認識されました。
本研究の結果は、OBP-702を介した腫瘍細胞上のp53エピトープ提示が、Ad-p53 DCsによるp53標的免疫の効果を高めることを示唆しています。
はじめに(Introduction)
樹状細胞(DC)ベースのワクチン療法は、腫瘍関連抗原(TAA)を提示するDCを用いてTAA特異的な細胞傷害性T細胞(CTL)を誘導する免疫療法の一種です¹。腫瘍抑制遺伝子p53は最も頻繁に変異を受ける遺伝子の1つであり、変異型p53タンパク質は多くのがんで過剰発現しています²。
p53タンパク質由来の変異型または野生型p53エピトープは、がん細胞上で主要組織適合複合体(MHC)分子の文脈でTAAとして提示されます³。変異型p53の新規エピトープはTAAとして免疫原性を有しますが、それらを標的とするCTLは、p53遺伝子に同一の変異を持つがんの限られた集団にのみ適用可能です⁴。
したがって、野生型p53エピトープは、より広く用いられており、これは多くの腫瘍細胞が変異型p53タンパク質を発現していても、野生型p53エピトープを標的とするCTLによって認識され得るためです³,⁴。
これまでに、野生型p53エピトープを標的としたDCベースのワクチン療法が複数開発されており、p53を標的とするCTLを誘導することを目的としています⁵。たとえば、野生型p53を発現する複製欠損型アデノウイルス(Ad-p53)や改変ワクシニアアンカラウイルス(p53MVA)をDCに導入し、化学療法と併用してがん患者を治療する臨床研究が実施されています⁵。
Ad-p53 DCまたはp53MVA DCを用いた免疫療法は、前臨床および臨床試験においてp53特異的なCTLを誘導することが示されています⁵。しかしながら、野生型p53を標的とするDCワクチン療法の抗腫瘍効果は、以下の要因によって制限されています:
-
腫瘍細胞におけるp53の免疫原性の弱さ
-
CTLの腫瘍浸潤が不十分であること
-
免疫抑制的な腫瘍微小環境(TME)の存在
したがって、腫瘍細胞内でp53の免疫原性を活性化し、CTLの腫瘍浸潤を促進する新しい抗腫瘍モダリティの開発が、p53標的DCワクチン療法の抗腫瘍効果を向上させるために必要とされています。
腫瘍溶解性ウイルス療法と本研究の目的
腫瘍溶解性ウイルス療法は、化学療法、放射線療法、免疫療法と併用することで、新たな抗腫瘍モダリティとして注目されています⁶⁷。
我々は、テロメラーゼ特異的で複製能を持つ腫瘍溶解性アデノウイルス「OBP-301(スラタデノチュレブ)」を開発しました⁸。OBP-301は、テロメラーゼ活性を有する悪性腫瘍細胞に対して幅広い抗腫瘍活性を示します⁹。また、OBP-301は以下の治療法に対する感受性を高める可能性を持ちます:
-
化学療法¹⁰
-
放射線療法¹¹
-
免疫チェックポイント阻害剤(ICIs)¹²
さらに、我々はOBP-301の治療効果を高める目的で、腫瘍抑制遺伝子p53を発現させるp53導入型ウイルス「OBP-702」を新たに作製しました¹³。OBP-702は、p53シグナル経路の活性化を介して、非導入型のOBP-301よりも強い抗腫瘍効果を発揮し、腫瘍細胞のアポトーシス(細胞死)およびオートファジー(自己融解)を誘導します¹⁴。
OBP-702によるp53過剰発現は、マウス腫瘍細胞において免疫原性細胞死を誘導し、CD8+ CTLの腫瘍浸潤を促進し、免疫チェックポイント阻害剤の抗腫瘍効果を増強することが報告されています¹⁵。また、OBP-702は、化学療法に抵抗性を示すマウス膵臓がんモデルにおいて、免疫抑制性の骨髄由来抑制細胞(MDSCs)の腫瘍浸潤を抑制することも示されています¹⁶。
これらの知見は、OBP-702が腫瘍細胞におけるp53発現を活性化し、CTLの腫瘍浸潤を促進する治療的可能性を持つことを示唆しています。
本研究の仮説
そこで我々は、OBP-702との併用治療により、腫瘍細胞内のp53免疫原性が活性化され、CTLの腫瘍浸潤が促進されることで、Ad-p53 DCワクチン療法の抗腫瘍効果が向上すると仮定しました。
本研究の目的
本研究では、マウス大腸がん(colon cancer, CC)腫瘍モデルにおいて、Ad-p53 DCsとOBP-702の併用効果を以下の点で検討しました:
-
使用モデル:CT26(p53野生型)およびMC38(p53変異型)細胞
-
DC成熟マーカーのフローサイトメトリーによる解析
-
単側および両側の皮下CC腫瘍モデルを用いた治療効果と腫瘍微小環境(TME)の変化
-
Ad-p53 DCおよびOBP-702処理腫瘍細胞におけるMHC分子を介したp53エピトープ提示の免疫ペプチドオミクス解析
-
OBP-702処理腫瘍細胞におけるp53エピトープ応答CTLの解析
結果
Ad-p53 DCsの特性評価(Characterization of Ad-p53 DCs)
Ad-p53 DCsを得るために、C57BL/6Jマウスの大腿骨から分離した骨髄由来樹状細胞(BMDCs)を、GM-CSF(顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子)およびIL-4(インターロイキン-4)と共に5日間培養し、その後、複製不能なAd-p53で2日間感染させました(図1A、補足図1A)。
対照として、E1A領域を欠損したアデノウイルスDL312(補足図1B)で感染させたDC(DL312 DCs)も用意しました。
リアルタイムPCR解析では、対照DCやDL312 DCsと比べて、Ad-p53 DCsでヒトp53 mRNAの発現が有意に上昇していることが示されました(図1B、補足図2)。
免疫細胞化学解析でも、Ad-p53で感染させたDC内にヒトp53タンパク質の発現が確認されました(図1C)。
さらに、Ad-p53 DCsの成熟度を評価するため、CD11c+ DCにおける以下のマーカーの発現をフローサイトメトリーにより解析しました(補足図3):
-
DC成熟マーカー:CD86, MHCクラスII(MHC-II), CD103
-
DC移動マーカー:CCR7
その結果、Ad-p53 DCsおよびDL312 DCsは、対照DCと比較して、上記マーカーを発現するCD11c+ DCの割合が有意に高いことがわかりました(図1D)。
これらの結果から、Ad-p53 DCsはヒトp53タンパク質を発現する成熟したDCを含むことが示唆されます。
ウイルス導入DCのリンパ節への移行(Migration of virus-transduced DCs to lymph nodes)
樹状細胞(DC)は、局所リンパ節(LNs)においてT細胞へ腫瘍関連抗原(TAA)を提示する上で重要な役割を担っています¹⁷。
本研究では、アデノウイルスで導入したDCが局所リンパ節へ移行可能かを確認するため、緑色蛍光タンパク質(GFP)を発現するアデノウイルス(Ad-GFP)で感染させたDC(Ad-GFP DCs)をマウスの左足底に注射し、24時間後に左鼠径リンパ節を摘出しました。
その結果、Ad-GFP DCsを接種したマウスでは、摘出したリンパ節においてGFPの蛍光シグナルが確認されました(補足図4)。
これにより、アデノウイルス感染DCは局所リンパ節へ移行できることが示唆されました。
Ad-p53 DCsとOBP-702併用療法のp53野生型CT26腫瘍におけるin vivo抗腫瘍効果
併用療法の治療効果を評価するため、p53野生型タンパク質を低発現するCT26大腸がん細胞株を用いました¹⁸。
まず、CT26細胞にOBP-702を72時間感染させたところ、細胞生存率は用量依存的に低下しました(図2A)。
次に、OBP-702で24時間および72時間感染させたCT26細胞において、リアルタイムRT-PCRとウエスタンブロット解析を用いて、ヒトp53 mRNAおよびタンパク質の発現が確認されました(図2B・C、補足図5)。
これらの結果は、CT26細胞がOBP-702によるウイルス性細胞傷害作用およびp53活性化に対して感受性が高いことを示唆します。
in vivo試験:
p53野生型CT26細胞による皮下腫瘍モデルをマウスに作製し、併用療法の治療効果を評価しました。
過去の研究で、Ad-p53 DCによる2回の免疫接種が効果的に抗p53免疫応答を誘導することが示されています¹⁹。
そこで本研究では、以下のスケジュールでAd-p53 DCsをマウスに皮下注射しました:
-
腫瘍接種前:−21日、−14日、−7日
-
腫瘍接種後:+6日
CT26腫瘍を接種したマウスには、腫瘍接種から7日目および10日目にOBP-702を腫瘍内注射しました(図2D)。
その結果、Ad-p53 DCsとOBP-702の併用療法は、対照群および単剤治療群と比較して、腫瘍の増殖を有意に抑制しました(図2E・F)。
また、摘出腫瘍の重量も併用群で有意に軽くなりました(図2G)。
以上の結果から、OBP-702との併用は、Ad-p53 DCsの抗腫瘍効果を著しく増強することが示されました。
Ad-p53 DCsとOBP-702の併用によるCT26腫瘍における抗腫瘍免疫応答の増強
(Enhancement of the antitumor immune response in CT26 tumors treated with Ad-p53 DCs and OBP-702)
併用療法が腫瘍微小環境(TME)における免疫状態をどのように変化させるかを評価するため、CD8⁺T細胞およびCD11c⁺樹状細胞(DC)の割合を免疫組織化学およびフローサイトメトリーで解析しました(補足図6および7)。
免疫組織化学解析の結果、CD8⁺T細胞およびCD11c⁺DCの数は、併用療法を受けた腫瘍で、対照群や単剤治療群と比較して有意に多くなっていました(図3A・B)。
フローサイトメトリー解析においても、併用療法を施した腫瘍は、対照および単剤治療群よりもCD8⁺CTLおよびCD11c⁺DCの割合が有意に高いことが確認されました(図3C)。
さらに、以下の活性化マーカーを発現するT細胞の割合も評価しました:
-
CD8⁺CD137⁺(抗原特異的T細胞マーカー)²⁰
-
CD8⁺CD69⁺(メモリーT細胞マーカー)²¹
-
CD8⁺PD-1⁺(抗原認識中のT細胞マーカー)²²
その結果、併用療法群ではこれらのマーカーを発現するT細胞の割合も、対照および単剤治療群と比較して有意に増加していました(図3C)。
これらのデータは、OBP-702との併用がAd-p53 DCsによる抗腫瘍効果を増強し、CD8⁺CTLおよびDCの腫瘍浸潤を促進することを示しています。
OBP-702はT細胞依存性の抗腫瘍免疫応答を活性化することでAd-p53 DCsの効果を増強する
(OBP-702 enhances the antitumor efficacy of Ad-p53 DCs via activation of the antitumor immune response)
まず、併用療法におけるT細胞の役割を明らかにするため、T細胞を欠損しているヌードマウス(athymic nude mice)を用いて同様の治療を行ったところ、Ad-p53 DCs+OBP-702の併用効果は大幅に低下しました(図4A)。
この結果は、T細胞が併用療法における抗腫瘍効果に不可欠であることを示しています。
また、併用療法においてp53標的のCTLが果たす役割を調べるため、p53を導入していない腫瘍溶解性アデノウイルス(OBP-301)を用いて、Ad-p53 DCワクチンとの併用効果を検討しました。
しかし、OBP-301との併用では抗腫瘍効果の増強はみられませんでした(図4B)。
これにより、OBP-702による腫瘍細胞内p53の活性化が、Ad-p53 DCによるp53標的CTL誘導の効果を高める鍵であることが分かりました。
併用療法によって長期的な全身抗腫瘍免疫が誘導される
(Combination therapy induces systemic antitumor immunity)
併用療法により完全奏効(CR)を示したマウス3匹と、治療を受けていない対照マウスを用いて、再挑戦試験(rechallenge test)を実施しました。
右側背部にはCT26細胞(元のがん細胞株)、左側背部には4T1乳がん細胞を同時に接種したところ:
-
CT26細胞は、対照マウスでは腫瘍形成したが、CRマウスでは腫瘍形成しませんでした(図4C)
-
4T1細胞は、両群で同程度の腫瘍形成を示しました(補足図8)
この結果から、併用療法によりCT26に対する長期的かつ特異的な抗腫瘍免疫が形成されたことが示唆されます。
アブスコパル効果(abscopal effect)の確認
(Systemic antitumor effect observed in untreated tumors)
次に、併用療法が未治療の腫瘍にも波及効果(アブスコパル効果)を及ぼすかを評価するため、両側皮下CT26腫瘍モデルを用いました(補足図9)。
-
一方の腫瘍には、Ad-p53 DCs単独、OBP-702単独、または併用療法を投与
-
もう一方の腫瘍には一切治療を行わない(未治療)
結果:
-
併用療法は、治療側だけでなく、未治療側の腫瘍の増殖も有意に抑制しました(図4D)
-
一方、Ad-p53 DCs単独やOBP-702単独では、治療側の腫瘍は抑制されましたが、未治療側には効果がありませんでした
免疫組織化学解析では、未治療腫瘍においてもCD8⁺T細胞およびCD11c⁺DCの浸潤が増加していることが確認されました(図4E・F)。
これらの結果は、Ad-p53 DCs+OBP-702の併用療法が全身的な抗腫瘍免疫応答を引き起こし、アブスコパル効果をもたらすことを示しています。
Ad-p53 DCsおよびOBP-702感染腫瘍細胞が共通して提示するp53由来ペプチドの同定
(Identification of p53-derived peptides commonly bound to MHC molecules on the surfaces of Ad-p53 DCs and OBP-702-infected tumor cells)
ヒトおよびマウスの腫瘍細胞において、OBP-702がp53の過剰発現を誘導することはすでに示されています¹³,¹⁵。
したがって、OBP-702で感染した腫瘍細胞は、Ad-p53 DCによって誘導されたCTLに対してより高い感受性を示す可能性があります。
この仮説を検証するために、Ad-p53 DCsで免疫されたマウスと非免疫マウスから脾細胞を採取し、IL-2で刺激してCD8⁺T細胞を誘導しました。
これらのCD8⁺T細胞を、OBP-702感染細胞または非感染CT26細胞と6時間共培養した後、IFN-γおよびグランザイムBを発現するCD8⁺T細胞の割合をFACS解析で評価しました(補足図10)。
結果:
-
OBP-702感染CT26細胞と共培養した場合、Ad-p53 DC免疫マウス由来CD8⁺T細胞は、IFN-γ⁺およびグランザイムB⁺細胞の割合が有意に増加しました
-
非感染CT26細胞との共培養ではこの効果は見られませんでした(図5A)
➡️ これらの結果は、Ad-p53 DCワクチン療法が、OBP-702感染腫瘍細胞を標的とするCTLを誘導することを示しています。
p53由来ペプチドの免疫ペプチドオミクス解析
Ad-p53 DCsは、MHC-IおよびMHC-IIに結合したp53ペプチドを提示することが知られており、これによりCD8⁺およびCD4⁺T細胞が誘導されます¹⁹。
本研究では、**免疫ペプチドオミクス(immunopeptidomics)**の手法を用いて、以下の細胞からMHC結合ペプチドを単離・質量分析しました²³:
-
MHC-I:
- コントロールCT26細胞
- OBP-301感染CT26細胞
- OBP-702感染CT26細胞 -
MHC-II:
- コントロールDC
- DL312 DC
- Ad-p53 DC
人p53タンパク質由来の全ペプチド配列のうち、マウスp53と共通の配列を含むものや、コントロール由来のMHC-I/IIに含まれるものは解析対象から除外しました(内因性p53由来と区別できないため)。
その結果:
-
Ad-p53 DCsおよびOBP-702感染CT26細胞は、いずれもMHCに結合したp53の63–79番アミノ酸配列(APRMPEAAPPVAPAPAA)を提示していることが判明しました(図5B、補足表1)
➡️ これは、人p53由来ペプチド(p5363–79)が、DCと腫瘍細胞の両方で提示され、免疫応答の共通ターゲットになり得ることを示します。
ELISPOTアッセイによるp53ペプチドに対するCTL応答の評価
(Evaluation of CTL responses to p53 peptides using ELISPOT assay)
次に、p53ペプチドが腫瘍抗原(tumor antigen)として機能するかどうかを確認するために、合成ペプチドを用いたELISPOTアッセイを実施しました。使用したペプチドは以下の3種類のヒトp53由来配列です:
-
p53⁶³⁻⁷⁰:APRMPEAA
-
p53⁶⁵⁻⁷³:RMPEAAPPV
-
p53⁷²⁻⁷⁹:PVAPAPAA
Ad-p53 DC免疫マウスと対照マウスから脾細胞を採取し、IL-2で刺激後、上記ペプチド混合物と72時間共培養しました。その後、IFN-γ産生細胞数をELISPOTで評価しました。
結果:
-
Ad-p53 DC免疫マウスからの脾細胞は、p53ペプチド混合物に反応して明確な**CD8⁺T細胞応答(IFN-γスポット形成)**を示しました(図5C)
➡️ これは、OBP-702感染腫瘍細胞が提示するp53ペプチドに対して、Ad-p53 DCワクチンによって誘導されたCTLが反応することを意味します。
Ad-p53 DCワクチンによるp53ペプチド特異的CTLの誘導評価(フローサイトメトリー)
さらに、Ad-p53 DCワクチンがp53ペプチド特異的CTLを誘導できるかを、フローサイトメトリーにより検証しました。
方法:
-
Ad-p53 DC免疫マウスと対照マウスから脾細胞を採取
-
IL-2で刺激し、CD8⁺T細胞を誘導
-
合成p53ペプチド混合物と6時間共培養
-
IFN-γおよびグランザイムBの発現をFACSで評価(図5D)
結果:
-
Ad-p53 DC免疫マウス由来のCD8⁺T細胞は、IFN-γ⁺およびグランザイムB⁺CD8⁺T細胞の割合が有意に高く、対照群よりも強い反応を示しました
➡️ これにより、Ad-p53 DCワクチンがp53ペプチドを標的とするCTLを有効に誘導することが示されました。
p53変異型MC38腫瘍モデルにおけるAd-p53 DCおよびOBP-702併用療法のin vivo抗腫瘍効果
(In vivo antitumor effect of Ad-p53 DC and OBP-702 combination therapy against p53-mutant MC38 tumors)
次に、p53変異型のマウス大腸がん細胞株であるMC38を用いて、Ad-p53 DCsおよびOBP-702の併用療法の治療効果を検証しました。MC38細胞は変異型p53を過剰発現しています¹⁸。
まず、OBP-702を72時間感染させたMC38細胞では、XTTアッセイにおいて細胞生存率が用量依存的に有意に低下しました(図6A)。
さらに、感染後24時間でリアルタイムRT-PCRおよびウエスタンブロット解析を行ったところ、ヒトp53 mRNAおよびタンパク質の発現が有意に増加しました(図6B・C、補足図5)。
➡️ このことから、MC38細胞もOBP-702のウイルス性細胞障害効果およびp53活性化に感受性があると示されました。
Ad-p53 DC単独療法では不十分
p53変異型MC38腫瘍に対して、Ad-p53 DCs単独療法での効果も検証されましたが:
-
**4回の定期的皮下注射(−21日, −14日, −7日, +6日)**を行ったにも関わらず、単独療法では腫瘍増殖の抑制効果は認められませんでした(図6D)
➡️ これは、p53変異型腫瘍に対しては、Ad-p53 DC単体では効果が不十分であることを示しています。
OBP-702との併用で治療効果が復活
次に、OBP-702との併用療法を同様のMC38腫瘍モデルで検証したところ:
-
Ad-p53 DCsとOBP-702の併用群では、対照群および単剤治療群と比べて腫瘍の増殖が有意に抑制されました(図6F・G)
-
免疫組織化学解析では、CD8⁺T細胞およびCD11c⁺DCの腫瘍内浸潤が有意に増加していました(図6H・I)
OBP-702感染MC38細胞のp53ペプチド提示
免疫ペプチドオミクス解析により、OBP-702で感染したMC38細胞からは、人p53由来の63–75番ペプチド(APRMPEAAPPVAP)がMHC-I分子に結合して提示されていることが判明しました。
この配列は、先にCT26細胞で検出されたペプチドと同一であり、変異型p53腫瘍でも共通のエピトープが提示されることを示唆します(補足表1)。
全身性免疫応答の誘導評価(LDHアッセイ)
併用療法がMC38に対する全身的なCTL反応を誘導しているかを評価するために、以下の手順でLDHアッセイを実施しました:
-
Ad-p53 DC+OBP-702治療マウスおよび対照マウスから脾細胞を採取
-
IL-2で7日間刺激し、CD8⁺T細胞を誘導
-
放射線照射したMC38細胞と24時間共培養
-
腫瘍細胞から放出された**LDH量(細胞障害の指標)**を測定
結果:
-
併用療法マウス由来CD8⁺T細胞は、MC38細胞に対して有意に多くのLDHを放出させ、対照群に比べて強い細胞傷害活性を示しました(図6J)
➡️ OBP-702との併用療法は、p53変異型MC38腫瘍においても有効であり、CTLを介した抗腫瘍免疫応答を活性化することが確認されました。
考察(Discussion)
樹状細胞(DC)を用いたワクチン療法は、腫瘍特異的な細胞傷害性T細胞(CTL)を活性化させる有望な免疫治療法であることが示されています¹。
しかし、いわゆる「コールド・チューモア(免疫学的に不活発な腫瘍)」では、腫瘍の免疫原性が弱く、CTLの腫瘍浸潤が乏しい上に免疫抑制的な腫瘍微小環境(TME)が存在するため、DCワクチン療法に対して耐性を示すことが多いとされています²⁶。
したがって、腫瘍の免疫原性および抗腫瘍免疫応答を高める新たな免疫療法との併用が、DCワクチン療法の効果を最大限に引き出す上で重要とされています。
本研究の主な知見
本研究では、以下のことが明らかとなりました:
-
Ad-p53 DCsとOBP-702の併用療法は、p53野生型・変異型のマウス大腸がん腫瘍モデルの両方において腫瘍増殖を著しく抑制した
-
この抑制効果は、腫瘍浸潤CD8⁺CTLおよびCD11c⁺DCの活性化を伴っていました
-
**OBP-702未治療の腫瘍にも抗腫瘍効果(アブスコパル効果)**を示し、全身性免疫応答を誘導しました
-
免疫ペプチドオミクス解析により、OBP-702感染腫瘍細胞およびAd-p53 DCsの両方が、p5363–79ペプチド(APRMPEAAPPVAPAPAA)を提示していることが判明しました
-
このペプチドに特異的なCTLが、OBP-702感染腫瘍細胞を選択的に除去しました
➡️ 以上より、OBP-702を用いたp53導入ウイルス療法とAd-p53 DCワクチン療法の併用は、p53抗原の提示とそれに応答するCTLの腫瘍動員を活性化し、強力な抗腫瘍効果を発揮する新たな戦略であると結論づけられます。
既存療法との比較とOBP-702の利点
これまでの研究でも、Ad-p53 DCワクチンはp53発現腫瘍を標的とするCTLを誘導できる有望な戦略であると報告されてきました⁵。
しかし、p53野生型腫瘍においてはp53の発現量が少ないため、CTLの効果が限定的になるのが課題でした。
今回のCT26モデルでは、OBP-702との併用により、Ad-p53 DCの効果が大幅に増強されたことから、腫瘍細胞側でp53の免疫原性を高めるOBP-702の併用は極めて有効であると考えられます。
p53活性化の代替手段としては:
-
MDM2阻害剤(腫瘍細胞のp53活性化を促進)²⁷,²⁸
-
化学療法(p53を間接的に活性化)²⁹
などがありますが、これらは正常細胞のp53も活性化してしまい、副作用のリスクがあるため、腫瘍特異的にp53を発現させるOBP-702は安全性の面でも有利です。
共通エピトープの提示と将来的展望
今回同定されたp5363–75(APRMPEAAPPVAP)などのペプチドは、MHC-IおよびMHC-IIを通じてDCおよび腫瘍細胞に共通して提示されることが示されました。
このうちp5365–73(RMPEAAPPV)は、HLA-A2拘束性エピトープとしても報告があり、ヒトへの応用可能性が高いと考えられます³⁰。
➡️ よって、今後の研究では、Ad-p53 DC+OBP-702併用療法がヒト大腸がんなどへの応用に有効かどうか、さらに検証が必要です。
アブスコパル効果と免疫記憶
本研究では、併用療法が未治療腫瘍にも効果を及ぼすアブスコパル効果を示し、さらに治癒したマウスでは再接種しても同じ腫瘍が形成されないという免疫記憶も確認されました。
この現象は、放射線治療やマイクロ波アブレーション、ウイルス療法(例:OBP-502)などでも報告されており¹²,³²,³³。
最近の研究では、OBP-702の投与により、**CD8⁺常在型記憶T細胞(T_RM)**の誘導を介して持続的な抗腫瘍効果が得られることも示されています³⁴。
投与経路に関する考察
本研究では、Ad-p53 DCは皮下投与によりT細胞応答を誘導しましたが、腫瘍内投与も有効である可能性があります³⁵,³⁶。
今後は、OBP-702とAd-p53 DCの両者を腫瘍内に併用投与することで、より強力な腫瘍特異的CTL応答が得られる可能性があると考えられます。
結論
本研究は、p53を導入した腫瘍溶解性アデノウイルス「OBP-702」が、Ad-p53 DCワクチンの抗腫瘍効果を高めることを示しました。
そのメカニズムは、MHC分子に結合したp53ペプチドの提示を介して、p53特異的CTLを腫瘍へ誘導し、強力な免疫応答を引き起こすものです。
➡️ これらの結果は、Ad-p53 DC+OBP-702の併用療法が、新たな抗腫瘍免疫療法の基盤として期待されることを強く示唆しています。
材料と方法(Materials and Methods)
細胞株(Cell lines)
以下のマウス由来がん細胞株を用いました:
-
CT26大腸がん細胞および4T1乳がん細胞(いずれもBALB/cマウス由来):
入手先:American Type Culture Collection(ATCC, 米国バージニア州マナッサス) -
MC38大腸がん細胞(C57BL/6マウス由来):
入手先:Kerafast(米国マサチューセッツ州ボストン)
CT26細胞はp53野生型、MC38細胞はp53変異型タンパク質を発現しています¹⁸。
-
CT26細胞の培養条件:RPMI-1640培地+10%ウシ胎児血清(FBS)
-
MC38細胞の培養条件:DMEM培地+10% FBS
-
共通条件:100 U/mLペニシリン、100 μg/mLストレプトマイシンを添加
遺伝子組換えアデノウイルス(Recombinant adenoviruses)
使用したアデノウイルスは以下の通りです:
-
OBP-301(スラタデノチュレブ):テロメラーゼ特異的な複製能を持つアデノウイルス。
hTERTプロモーターによりE1AおよびE1B遺伝子の発現を制御。以前に構築済み⁸⁹。 -
OBP-702:OBP-301のE3領域にEgr-1プロモーター制御下のヒトp53発現カセットを挿入して作製¹³。
腫瘍特異的にp53を発現。 -
Ad-p53:複製不能型アデノウイルスで、ヒト野生型p53を発現。DCへの遺伝子導入に使用(補足図1A)
-
DL312:E1A領域が欠損した複製不能型アデノウイルスで、Ad-p53 DCの対照に使用(補足図1B)
いずれのウイルスも、塩化セシウム密度勾配超遠心法で精製し、293細胞でプラークアッセイにより力価(PFU)を測定後、−80°Cで保存。
Ad-p53 DCの調製(Preparation of Ad-p53 DCs)
マウス骨髄由来細胞(BMDC)は以下のようにして調製しました:
-
マウス種:BALB/cおよびC57BL/6J(CLEA Japan社より購入)
-
麻酔:2%イソフルラン吸入後、頸椎脱臼にて安楽死
-
骨髄抽出部位:大腿骨
-
分化誘導:
- GM-CSF(40 ng/mL, Sigma)
- IL-4(10 ng/mL, Sigma)
で5日間培養 -
ウイルス感染:
- Ad-p53またはDL312(各MOI = 100 PFU/細胞)で2日間感染
- 得られたDCを、それぞれAd-p53 DCsまたはDL312 DCsとして使用
定量リアルタイムPCR(Quantitative real-time PCR)
RNA抽出およびcDNA合成:
-
対象:コントロールDC、DL312 DC、Ad-p53 DC
-
抽出キット:miRNeasy Mini Kit(Qiagen, 米国)
-
cDNA合成:TaqManリバーストランスクリプションキット(Applied Biosystems)
リアルタイムPCR測定:
-
装置:StepOne-Plus™(Applied Biosystems)
-
プライマー:
- ヒトp53:TP53(Hs01034253_m1)
- 内部対照:Gapdh(Mm99999915_g1)、Actb(Mm02619580_g1)
発現量は**ΔΔCt法(2^-ΔΔCt)**により算出し、GAPDHまたはActbで正規化(図1B、補足図2)。
免疫細胞染色(Immunocytochemistry)
-
DCは1×10⁶細胞/ウェルの密度で12ウェルプレートに播種
-
固定液:4%パラホルムアルデヒド
-
透過処理:メタノール
-
一次抗体:ヒトp53(1:800、Cell Signaling Technology)
-
二次抗体:Alexa Fluor 647(1:500、Invitrogen)
-
核染色:DAPI
-
撮像:共焦点レーザースキャニング顕微鏡(IX83、Olympus)
フローサイトメトリー解析(Flow cytometric analysis)
解析対象:
-
DC成熟マーカー:CD11c, CD86, CD103, CCR7, MHC-II
-
腫瘍内免疫細胞:CD45⁺造血細胞、CD8⁺T細胞、CD11c⁺DC
-
CD8⁺T細胞の活性化マーカー:CD137, CD69, PD-1
解析方法:
-
蛍光標識一次抗体で染色
-
同種対照IgGにて陰性コントロール
-
測定機器:BD FACSLyric または FACSAria
-
データ解析:FlowJo ver. 7.6.5
Ad-GFP-DCの調製と生体内分布評価(Preparation and biodistribution of Ad-GFP-DCs)
-
BALB/cマウスの大腿骨からBMDCを採取
-
GM-CSF(40 ng/mL)とIL-4(10 ng/mL)で5日間培養
-
複製不能なAd-GFP(MOI = 100)で2日間感染 → Ad-GFP-DCを得る
生体内分布試験:
-
マウス左足底にAd-GFP-DCまたはコントロールDCを皮下投与
-
24時間後、左鼠径リンパ節を摘出し、凍結切片を作製
-
顕微鏡:IX83(Olympus)による蛍光観察
細胞生存率アッセイ(XTT assay)
-
OBP-702(またはOBP-301)を、CT26またはMC38細胞にさまざまなMOI(Multiplicity of Infection)で感染させ、72時間培養
-
細胞生存率は、XTTアッセイを用いて測定:
- 試薬:Cell Proliferation Kit II(Roche)
- 吸光度測定:450 nmで測定(基準波長650 nm) -
生存率は、未感染細胞を100%として相対的に算出(図2A、図6A)
ウエスタンブロット解析(Western blotting)
-
感染後24時間のCT26またはMC38細胞を収集し、RIPAバッファーでタンパク質を抽出
-
SDS-PAGEで分離後、PVDF膜へ転写
-
一次抗体:
- ヒトp53(DO-1, 1:500, Cell Signaling Technology)
- GAPDH(1:1000, Santa Cruz) -
二次抗体:HRP結合抗マウスIgG
-
発色検出:ECLシステム(GE Healthcare)を使用
-
イメージング装置:ImageQuant LAS 4000(GE Healthcare)またはChemiDoc(Bio-Rad)
マウス皮下腫瘍モデルと治療スケジュール
(Mouse subcutaneous tumor models and treatment schedule)
腫瘍モデルの作成:
-
BALB/cまたはC57BL/6Jマウスの右背部皮下に:
- **CT26細胞(1×10⁶個)**または
- **MC38細胞(5×10⁵個)**を注射して腫瘍を形成
治療スケジュール:
-
DCワクチン接種:
- Day −21, −14, −7 にAd-p53 DCまたはDL312 DCを皮下注(足底)
- Day +6 に追加接種 -
ウイルス療法(OBP-702など):
- Day +7 および Day +10 に、腫瘍内へウイルス(1×10⁸ PFU)を注射
アブスコパル効果の検証:
-
両側腫瘍モデル:
- 右側腫瘍:治療実施(ウイルスまたはDC)
- 左側腫瘍:未治療として効果の波及を評価
再挑戦実験(Rechallenge test):
-
完全奏効(CR)を示したマウスを用いて:
- CT26細胞(右側)、4T1細胞(左側)を同時皮下接種
- 腫瘍形成の有無を観察
免疫組織化学(Immunohistochemistry, IHC)
-
腫瘍を摘出後、4%パラホルムアルデヒドで固定し、パラフィン包埋
-
5 µm厚のスライドを作製し、抗原賦活処理(Tris-EDTA緩衝液中で加熱処理)を実施
-
主な一次抗体:
- CD8(1:100、Cell Signaling Technology)
- CD11c(1:100、Abcam) -
二次抗体:HRP標識抗ラビットIgG
-
発色:DAB(3,3′-ジアミノベンジジン)
-
カウンターステイン:ヘマトキシリン
-
観察:オリンパスIX83顕微鏡(Olympus)
※ CD8⁺T細胞およびCD11c⁺DCの腫瘍内浸潤を定量的に評価(図3A・B、図6H・I)
IFN-γ ELISPOTアッセイ
-
マウス脾臓由来単核細胞(splenocytes)をIL-2(10 ng/mL)とともに72時間刺激
-
合成p53ペプチドミックス(各5 μg/mL)と共培養
-
IFN-γ産生細胞の測定:ELISPOTプレート(R&D Systems)を使用
-
プレート洗浄後、ビオチン化抗IFN-γ抗体→ストレプトアビジン-HRP→発色基質(AEC)で染色
-
スポット数(IFN-γ産生細胞数)を画像解析装置で自動カウント(図5C)
免疫ペプチドオミクス解析(Immunopeptidomics)
目的:MHCクラスIおよびIIに結合したp53由来ペプチドの同定
手順:
-
細胞調製:
- CT26細胞(未感染、OBP-301感染、OBP-702感染)
- MC38細胞(未感染、OBP-702感染)
- DC(コントロール、DL312感染、Ad-p53感染) -
MHC-I/II複合体の単離:
- 抗MHC抗体で免疫沈降 -
ペプチド抽出とLC-MS/MS解析:
- 酸処理でMHCからペプチドを溶出
- LC-MS/MS(ナノ液体クロマトグラフィー+質量分析)で分析
- データ解析:Spectrum MillおよびUniProtタンパク質データベース使用
- マウスとヒトp53配列の一致領域に限り検索対象とする(p53特異性担保のため)
得られたペプチドは補足表1に一覧化(例:APRMPEAAPPVAPなど)
次回は【Cytotoxicity assay(細胞傷害性アッセイ)】と【統計解析】の邦訳で「材料と方法」の完了となります。続けてよろしいでしょうか?
細胞傷害性アッセイ(Cytotoxicity assay)
目的:Ad-p53 DC+OBP-702併用療法によって誘導されるCD8⁺T細胞の腫瘍細胞に対する殺傷活性を測定
手順:
-
T細胞の誘導:
- Ad-p53 DCs+OBP-702併用療法を受けたマウス、および対照マウスから脾細胞を採取
- IL-2(10 ng/mL)で7日間刺激してCD8⁺T細胞を活性化 -
標的細胞の準備:
- MC38細胞を50 Gyでγ線照射(死細胞による背景低減のため)
- 96ウェルプレートに播種(1×10⁴細胞/ウェル) -
共培養:
- Effector(T細胞)とTarget(腫瘍細胞)を E:T比 = 10:1 で24時間共培養 -
LDHアッセイによる細胞障害評価:
- 上清中の乳酸脱水素酵素(LDH)活性を測定(CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay Kit, Promega)
- 吸光度:490 nm
- 細胞溶解率(%)は以下で算出:
(実験LDH − スポンテインLDH) / (最大LDH − スポンテインLDH) × 100
統計解析(Statistical analysis)
-
すべての数値データは 平均 ± 標準誤差(SEM) で表記
-
統計ソフト:GraphPad Prism 9 を使用
-
比較方法:
- 2群間:非対応 t検定
- 複数群間:一元配置分散分析(ANOVA) → Dunnettの多重比較検定 -
有意水準:
- p < 0.05:有意差あり
- 記号の定義:
- p < 0.05 → *
- p < 0.01 → **
- p < 0.001 → ***
参考文献(前半 1–18)
-
Palucka, K. & Banchereau, J.
樹状細胞ワクチンに関する総説。
Nat Rev Cancer 12, 265–277 (2012) -
Hegde, P. S. & Chen, D. S.
腫瘍免疫における免疫「ホット」および「コールド」の区別と臨床的意義。
Clin Cancer Res 26, 4302–4308 (2020) -
Suda, T. & Wakabayashi, T.
テロメラーゼ特異的腫瘍溶解性アデノウイルスOBP-301(Telomelysin)の前臨床データ。
Curr Cancer Drug Targets 8, 416–425 (2008) -
Sato, Y. et al.
OBP-301によるテロメラーゼ特異的p53腫瘍抑制。
Mol Ther Oncolytics 15, 180–188 (2019) -
Kitamura, T. et al.
Ad-p53導入DCによる大腸がんモデルに対するT細胞応答誘導。
Cancer Sci 106, 1582–1590 (2015) -
Ito, M. et al.
同上:Ad-p53 DCワクチンの免疫原性と抗腫瘍効果。
J Immunother 38, 292–302 (2015) -
Hanahan, D. & Weinberg, R. A.
がんの特徴に関する有名な論文。
Cell 144, 646–674 (2011) -
Kanai, F. et al.
テロメラーゼ制御アデノウイルスによるヒト肝がんの標的治療。
Nat Med 7, 1213–1217 (2001) -
Tazawa, H. et al.
ヒト腫瘍細胞におけるOBP-301の特異的細胞溶解活性。
J Clin Invest 113, 1774–1781 (2004) -
Tazawa, H. et al.
OBP-301による抗腫瘍免疫増強。
Cancer Res 75, 4835–4846 (2015) -
Wakimoto, H. et al.
膠芽腫に対するOBP-301の放射線感受性向上効果。
Mol Ther 15, 1796–1803 (2007) -
Matsushima, K. et al.
マイクロ波アブレーション後の免疫応答に関する研究。
Cancer Sci 108, 1540–1547 (2017) -
Ota, Y. et al.
OBP-702の開発とin vitro・in vivoにおけるp53発現と細胞障害。
Mol Ther Oncolytics 16, 238–247 (2020) -
Sugawara, Y. et al.
アポトーシスとp53に関する腫瘍生物学研究。
Oncogene 28, 3563–3575 (2009) -
Kagawa, S. et al.
放射線との併用によるOBP-702の抗腫瘍増強。
Cancer Sci 111, 3060–3070 (2020) -
Zitvogel, L. et al.
免疫原性細胞死と抗腫瘍免疫の連携。
Immunity 39, 74–88 (2013) -
Smyth, M. J. et al.
免疫系ががんにどう関与するかの包括的レビュー。
Nat Rev Cancer 6, 928–938 (2006) -
Liu, Y. et al.
p53変異型MC38細胞に関する特性評価。
Cell Death Dis 10, 607 (2019) -
Yang, H. et al.
腫瘍微小環境におけるマクロファージの抗腫瘍効果とDC活性化の連携。
J Immunol 173, 4779–4791 (2004) -
Zhang, P. et al.
抗原特異的T細胞応答のモニタリングにおけるCD137の有用性。
Blood 120, 1390–1399 (2012) -
Walunas, T. L. et al.
T細胞活性化と免疫記憶におけるCD69の役割。
Immunol Rev 182, 200–210 (2001) -
Barber, D. L. et al.
慢性感染症モデルにおけるPD-1発現T細胞と免疫抑制。
Nature 439, 682–687 (2006) -
Spranger, S. et al.
がん免疫療法におけるDCとT細胞浸潤の役割。
J Clin Invest 125, 3341–3352 (2015) -
Roberts, N. J. et al.
ウイルスベクターによる腫瘍局所での免疫反応の活性化。
Science Transl Med 6, 221ra13 (2014) -
Ribas, A. et al.
腫瘍溶解性ウイルスと免疫チェックポイント阻害薬の併用に関する臨床研究。
Cell 170, 1109–1119.e10 (2017) -
Spranger, S. et al.
免疫コールド腫瘍のTME変化に関する解析。
Immunity 43, 724–736 (2015) -
Tovar, C. et al.
MDM2阻害剤によるp53再活性化のメカニズム。
Proc Natl Acad Sci USA 103, 1888–1893 (2006) -
Vassilev, L. T. et al.
ナットリン(Nutlin)によるp53誘導とがん細胞死の促進。
Science 303, 844–848 (2004) -
Kranz, D. M. et al.
化学療法により誘導される腫瘍抗原の提示と免疫効果。
Nature 425, 305–309 (2003) -
Theobald, M. et al.
HLA-A2拘束性p53ペプチドに対するCTLの誘導。
Proc Natl Acad Sci USA 92, 11993–11997 (1995) -
Liu, Y. et al.
放射線治療後のアブスコパル効果とその免疫学的基盤。
Cancer Lett 356, 180–190 (2015) -
Yamamoto, M. et al.
OBP-502の免疫記憶誘導とアブスコパル効果。
Cancer Gene Ther 28, 173–184 (2021) -
Sato, Y. et al.
テロメラーゼ特異的ウイルス療法による免疫刺激効果。
Mol Ther Oncolytics 27, 198–208 (2022) -
Sugawara, Y. et al.
OBP-702による腫瘍常在記憶T細胞の誘導。
Cancer Sci 113, 3858–3869 (2022) -
Kitamura, T. et al.
腫瘍内投与によるAd-p53 DCの活性化効果。
Int J Cancer 145, 2420–2429 (2019) -
Kitamura, T. et al.
腫瘍内注射によるDC活性化とT細胞動員。
Cancer Sci 112, 3911–3921 (2021) -
Hodi, F. S. et al.
免疫チェックポイント阻害薬の進展と併用戦略。
N Engl J Med 363, 711–723 (2010)
(とりあえずここまで)by シエン
4588オンコリスバイオファーマの将来性/がんを切らずに治す ウイルス療法テロメライシン
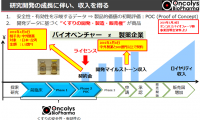
4588オンコリスバイオファーマ/2013年上場時の浦田社長インタビュー