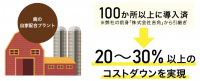こんにちは、シエン(@M12n08Jp)です。
本日で2025年前半が終わります、今年もまた上場株式・未上場株式投資 共に含み損状態で終わります。5年も待っているので、そろそろ上場バイオ株(オンコリス、デルタフライ)も株価上昇が始まって欲しいものですが、株価はまさかの底這い状態となっています。
会社概要と現在の状況
デルタフライ・ファーマ株式会社(東証グロース 4598)は、独自の「モジュール創薬」手法によって新規抗がん剤の研究開発を行う創薬ベンチャーです。モジュール創薬とは、特許切れや副作用で開発中止となった抗がん剤の活性物質を「モジュール(構成単位)」として組み合わせることで、新たな有効性・安全性バランスに優れた抗がん剤を創製するアプローチです。この方法により基礎研究工程を簡略化し、通常10年以上かかる抗がん剤開発を6~9年程度で承認可能にすることを目指しています。実際、同社の開発品は全て新規物質として特許化が可能で、開発期間が短く費用が少ない点が大きな強みとされています。
現在、デルタフライ社は6つのパイプラインを有し、2025年5月末時点でそのうち4品目が日米で臨床試験進行中(残り2品目は臨床試験準備中)です。最も開発が先行するのは急性骨髄性白血病(AML)向けの「DFP-10917」で、続いて膵臓がん向け「DFP-17729」や非小細胞肺がん向け「DFP-14323」などが控えています。同社はこれらの開発を着実に進め、2026年頃から順次承認申請を行う計画であり(DFP-10917は2026年3月期に米国申請準備、DFP-17729は2028年、DFP-14323は2029年予定)、複数のパイプラインの上市を目指しています。
同社のビジネスモデル上、現時点では自社製品販売収益はなく、主な収入源はライセンス契約による一時金やマイルストーン収入です。2025年3月期も事業収益ゼロで、研究開発先行に伴い営業損失17.08億円(前期13.03億円の損失)を計上しました。研究開発費は14.38億円(前年28.5%増)と増加しましたが、これは臨床試験の症例数拡大や次相試験に向けた製剤製造など積極投資の結果です。一方、財務基盤の安定化にも注力しており、2022年末と2023年10月には第三者割当増資と新株予約権発行で約12~13億円ずつの資金調達を実施し、開発資金を確保しています。2025年4月にも新株予約権と無担保社債の組み合わせで約10.7億円を調達し、追加で最大5億円の社債枠を設定するなど、研究開発を継続するための資金繰りを柔軟に行いました。
経営面では、同社は中期事業計画や数値目標を公表していません。その理由として、抗がん剤開発の収益はライセンス契約一時金やマイルストーンに依存しており、まだ製品売上による安定収益を得る段階にないためと説明しています。したがって単年度業績予想でも、不確実な収入(契約金等)は織り込んでいません。同社が最重要課題と考えるのは、パートナー企業との提携による承認取得と製品販売で安定収益源を確保することであり、まずはDFP-10917の承認・上市を成功させ、その収益を次のパイプライン投資に充てる「成功循環モデル」を描いています。
最近の業績推移と財務状況
デルタフライ・ファーマの直近業績は、創薬ベンチャーらしく赤字続きですが、研究開発投資は拡大傾向にあります。2025年3月期は売上ゼロ(前期もゼロ)で、営業損失17.08億円・最終損失17.21億円となりました。これは開発加速による研究開発費の増加(前年から21.7%増)によるもので、特に臨床試験の拡大や治験薬製造費用の発生が響きました。一方で2026年3月期の会社計画では、引き続き売上ゼロながら損失縮小(営業損失15.0億円の見通し)を掲げています。これは大型提携がまとまればマイルストーン収入獲得もあり得るものの、現時点では織り込まず、開発費用自体はピークアウトして減少に転じる見込みだからです。実際、2026年3月期は研究開発費を前期比▲15.7%の12.12億円に抑える予想となっています(主要パイプラインの試験進行にめどが立ち、費用圧縮を図るため)。
同社は資金調達面でも工夫を凝らしており、直近ではライセンス先との関係強化を兼ねた資金調達も実施しています。例えば2023年10月の第三者割当増資では約12.96億円を調達しましたが、割当先の選定にあたっては同社とDFP-17729(日本における独占販売・製造権)およびDFP-14323(日本における独占販売権)の2件のライセンス契約を結んでいる企業(=日本ケミファ)との関係性が考慮されたとみられます。実質的にパートナー企業との資本面での連携も深め、財務と開発の両面で安定性を確保しようという姿勢です。
また、自己資本の減少リスクへの対処も進めています。2022年12月と2023年10月の増資によって累計25億円超を調達したことで、2025年3月末時点の資本金は52.04億円となり、債務超過などの懸念は回避されています。もっとも、株式希薄化は避けられないため、経営陣としては一日も早く新薬を上市し、ライセンスロイヤリティや製剤供給収入によって黒字転換・自己資金創出を実現することが急務となっています。
なお、Shared Research社の分析によれば、デルタフライ社の強みは「短期間・低コストの開発手法」「全開発品の特許化(新規物質)」「大手企業との提携実績」であり、一方弱みとして「独自モデルへの認知度不足」「自社での新薬上市経験がない」「経営陣の後継者問題や人材確保」が指摘されています。認知度や人材面の課題はあるものの、既に日本新薬や日本ケミファといったパートナーとの協業実績がある点は信頼性につながります。同社は引き続き積極的なIRや学会発表を通じて知名度向上と人材確保にも努めており、これらの弱み克服にも取り組んでいます。
抗がん剤パイプラインの進捗状況
デルタフライ・ファーマの開発パイプラインの中でも、特に進捗が注目される3つのプロジェクトについて、その現状と展望をまとめます。
DFP-10917(再発・難治性AML治療薬)
DFP-10917は、再発または難治性の急性骨髄性白血病(AML)を対象とする抗がん剤です。既存のシタラビン系抗がん剤の低用量持続投与に着想を得た「細胞周期調節剤」で、米国では2019年4月に単剤の臨床第3相試験(第3次救援療法として)が開始されました。日本国内では提携先の日本新薬株式会社が第1相試験を担当しており、2021年2月に患者への投与を開始しています。
この薬剤は開発コードながら国際一般名(INN)「ラドゴシタビン」も付与されており、2022年11月には米国FDAからオーファンドラッグ(希少疾病用医薬品)指定を取得しました。オーファン指定により、承認後7年間の市場独占権(先発品排他権)が認められるほか、FDAとの相談・支援を受けやすくなるため、承認審査への追い風となります。
米国第3相試験は当初150症例の組入れを目標として進められていましたが、COVID-19流行の影響で症例登録に遅延が生じました。同社は治験実施施設を全米39施設に拡大して対応し、計画より約1年遅れたものの2023年5月に150例の登録完了を達成しています。その後、2024年2月頃に中間解析データ確定を目指してデータカットオフを行う予定でしたが、2024年1月末時点で長期生存中の患者が複数おり完全な生存期間(OS)の把握に時間を要することが判明しました。そこで同社は当面データカットオフを延期し、これら長期生存患者のフォローアップ継続を決定しました。この判断はポジティブにも捉えられ、治験群で生存期間の延長が示唆されている可能性が期待されています(なお二重盲検試験のため企業側は患者が治験群か対照群か把握できません)。
現在(2025年5月時点)、第3相試験データのクリーニング処理は完了間近となっており、2025年内にデータカットオフを行う準備が進められています。近々データを独立の安全性モニタリング委員会(DSMB)に提出し、優越性(DFP-10917群が対照群より有意に効果上回るか)の判定を仰ぐ予定です。有意差が確認でき次第、米国FDAへの新薬承認申請(NDA)に向けた作業も並行して開始する計画で、承認取得後に必要な製剤(凍結乾燥剤)の商用生産準備も進められています。つまり、2025年中にも中間解析(または最終解析)の結果が出揃い、良好であれば速やかに承認申請へ移行する体制が整いつつあります。
加えて、DFP-10917はベネトクラクス(VEN, 商品名ヴェネクレクスタ)との併用療法でも開発が進んでいます。ベネトクラクスは近年AML一次治療に承認された画期的新薬ですが、奏効しなかった患者向けの新たな治療として10917との併用が期待されています。デルタフライ社は2024年3月に併用療法の臨床第1/2相試験プロトコルをFDAに提出し、4月に実施許可を獲得して米国5施設で試験を開始しました。初回コホートの3例全てで4週間以内に白血病細胞が消失し完全寛解(CR/CRi)を確認するなど極めて良好な初期結果が得られ、2024年末までに6例全例で安全性が確認されたことから現在フェーズ2部分に移行しています。この併用療法に関する発明特許も米国・日本・台湾で成立済みで、2040年まで有効となっています。つまり、併用療法も将来の適応拡大として睨みつつ、早期から知財と治験を押さえている状況です。
なお、日本国内では先述のとおり日本新薬がDFP-10917の第1相試験を進めており、同社との契約により日本における開発・販売権は日本新薬が保有しています(米国を含む日本以外の地域はデルタフライ社が権利保持)。デルタフライ社は10917の国外展開に向けて、単剤と併用療法をパッケージにしたライセンスアウト交渉を世界的に行っており、解析結果が出た段階で条件交渉に入りたいという製薬企業候補も既に存在するといいます。これは、データ次第で大手製薬との提携(ライセンス契約)が早期にまとまる可能性を示唆しており、投資家から大きな期待を集めるポイントです。
DFP-14323(非小細胞肺がん免疫調整剤)
DFP-14323は、進行期の非小細胞肺がん(NSCLC)を対象とする経口抗がん剤です。元になった化合物は急性白血病治療薬「ウベニメクス」(商品名ベスタチン)で、免疫機能を改善する作用が知られていました。デルタフライ社はこのウベニメクスの抗腫瘍免疫賦活作用とがん幹細胞抑制作用に着目し、通常より低用量で単剤または他の抗がん剤・分子標的薬と併用することで高齢患者などの免疫機能低下時にも効果を発揮できるよう開発したのがDFP-14323です。要するに、がん患者の免疫力を底上げして治療効果を高める経口免疫調整剤と位置付けられます。
この薬剤は既承認薬の新適応拡大にあたるため、創薬段階の基礎研究を省略し、いきなり臨床第2相試験から開発を開始しました。2016年に協和化学工業と日本国内独占ライセンス契約を結び共同開発していましたが、協和側の事情で2020年11月に契約解消となり、以降はデルタフライ社が単独で開発を継続しています。2020年には日本・米国・欧州を含む主要国で特許を取得し、経口吸収率が極めて高く脳転移症例にも有用であることからPCT国際出願も完了させています(単剤および併用組成物に関する特許)。知財面は万全です。
臨床第2相試験(単剤+アファチニブ併用療法)は、日本の主要病院で2017~2020年に実施されました。対象はEGFR遺伝子変異陽性のステージIII/IV NSCLC患者(約40%が脳転移あり)で、症例登録を9施設に拡大して2020年3月に予定症例集積を完了。結果は非常に良好で、疾病制御率(DCR)100%を達成し、事前に設定した「第3相に移行する基準(DCR 87%以上)」を大きく上回りました。加えて奏効率(ORR)も65.4%以上と高い有効性を示し、その詳細データは2020年11月のESMO Asia学会でポスター発表されています。さらに追跡調査で無増悪生存期間(PFS)中央値が20.6か月と算定され、既存薬のアファチニブ(11.1か月)やオシメルチニブ(18.9か月)の成績を上回ることが確認されました。最終解析ではPFS 23.1か月、奏効率69.2%に達し、このデータはNSCLC領域では驚異的な良好さです。
こうした結果を受け、同社は条件付き早期承認(第3相試験を承認後に実施する前提での承認)も視野にPMDAと協議しましたが、最終的にPMDAからは「優越性検証のための第3相比較試験を実施すべし」との要請がありました。これを受け現在、第3相試験(大規模比較試験)が日本国内で進行中です。試験デザインは「DFP-14323+アファチニブ20mg/日」併用群 vs 「標準用量アファチニブ40mg/日」単独群という比較で、エンドポイントは無増悪生存期間(PFS)。全国約30施設で患者募集を行い、目標症例数は148例、2024年7月に第1例目を登録して以降、順調に組入れが進んでいます。一部治療継続患者のフォローアップ期間を延ばしたため試験完了予定は当初計画より1年程度遅れ2027年頃となりましたが、2025年5月時点で症例登録は計画通り順調と報告されています。なお、日本の肺癌診療ガイドライン(2024年改訂)において、EGFR変異陽性肺がんの一部でアファチニブが一番手推奨に位置づけられたこともあり、本試験への患者登録促進が期待できる状況です。
商業面では、日本国内の独占的販売権を日本ケミファ株式会社が握っています。2022年3月に日本ケミファと契約を締結し、デルタフライ社は契約一時金2億円を受領、さらに開発進捗に応じたマイルストーン合計最大43億円を受け取る権利を得ています。加えて、上市後の売上に応じた段階的ロイヤリティ(後半シングル~10%台)も支払われる契約です。契約条項から逆算しても、同社および日本ケミファは本剤の市場潜在力を相当に高く見積もっていることが伺えます。今後、第3相試験の成功と承認取得が見えれば、日本ケミファによる販売体制構築や海外展開に向けた新たな提携(日本国外ライセンスアウト)の可能性も出てくるでしょう。
DFP-17729(末期膵臓がん向け微小環境改善剤)
DFP-17729は、末期の膵臓がんなどを対象とした全く新しいコンセプトの経口抗がん剤です。腫瘍周辺の酸性化した微小環境をアルカリ化製剤で中和し、がん細胞の増殖を抑制する作用を狙っています。正常細胞周辺は弱アルカリ性ですが、がん細胞は乳酸など酸性物質を放出し周囲を酸性環境に変えることで、免疫細胞の攻撃から逃れ成長すると言われます。本剤はその酸性環境を中和して「がんが住みにくい環境」に変えることで効果を発揮する薬剤です。いわば腫瘍の”土壌”を改良する治療薬であり、免疫チェックポイント阻害剤など他治療との併用で相乗効果が期待されます。実際、動物実験ではDFP-17729で腫瘍環境をアルカリ化すると、抗PD-1/PD-L1抗体など免疫薬の効果が高まることが確認されています。また、日本で広く使われる経口抗がん剤TS-1(ティーエスワン)との併用でも、TS-1単剤に比べ腫瘍増殖を抑制する効果が示されています。
知的財産面では、本コンセプトに基づく発明を世界各国で出願中で、既に日本と韓国で特許取得済みです。日本国内ではDFP-17729に関する3件全ての特許が成立しており、同社は2020年3月に日本ケミファ社と日本における独占ライセンス契約(製造・販売権)を締結済みです。つまり、日本では承認取得次第、日本ケミファが製造・販売を担う形で、デルタフライ社はロイヤリティ等収入を得るモデルとなります。契約一時金として1億円を既に受領しており、臨床の進展に応じて追加マイルストーンも設定されています。
臨床開発の状況としては、フェーズ1/2複合試験を日本国内で実施し完了しています。まずフェーズ1部分で、安全性評価のため既存薬(TS-1またはゲムシタビン)+DFP-17729併用の投与を行い、関東の3施設で2021年4月までに必要症例を登録しました。全症例の安全性が確認されたため直ちにフェーズ2部分へ進み、フェーズ2では「TS-1またはジェムザール+DFP-17729併用群(22例) vs TS-1またはジェム単独群(11例)」の比較試験が組まれました。こちらも2021年4月に第1例目の投薬を開始し、主に関東の医療機関で症例登録が進められ、2024年3月期末時点でデータ解析が継続中と報告されています。このように1相から2相まで一気通貫で実施し、第3相も迅速に行う計画であったため、他パイプラインに比べ開発期間は短く承認申請まで進める見込みでした。コロナ禍で一部プロトコル見直し・遅延はあったものの、同社によれば依然として他品目より短い開発期間で済みそうとのことです。
これを踏まえ、2024年にはPMDAとの対面助言を実施し、フェーズ2/3統合試験の開始許可を得ました。そして2025年3月に国内第2/3相試験を開始しています。この試験は全国15施設で行われ、1日12グラム(3グラム×4回投与)のDFP-17729を投与、主要評価項目は全生存期間(OS)です。まずフェーズ2部分として76例(各群38例)を登録し、「DFP-17729+TS-1群 vs プラセボ+TS-1群」で有効性差を評価します。その結果に応じて必要症例数を調整しつつフェーズ3部分へ移行するアダプティブな設計となっており、フォローアップ期間も追加して開発を進める計画です。これにより承認申請予定時期は当初計画より延びて2028年3月期(2028年3月まで)となりましたが、着実に最終試験段階へと入っています。
DFP-17729はデルタフライ社のパイプライン中最も新しい部類ですが、上述のようにモジュール創薬のメリットを活かしてフェーズ統合・迅速開発が行われています。奏効メカニズムがユニークなため、膵臓がん以外の固形がん領域でも横展開できる潜在性も秘めています。免疫チェックポイント阻害薬との併用増強効果が確認されていることから、将来的には難治がん全般の免疫療法のバックボーン薬として発展する可能性もあります。まずは膵臓がん3次治療以降での有効性確認が当面の目標となりますが、ニーズの高い領域だけに、実用化されれば患者の生存期間延長に大きく貢献し得ると期待されています。
FDA・臨床試験に関するIR情報と知的財産状況
デルタフライ・ファーマのIR(投資家向け情報)からは、各パイプラインの規制当局対応や知財戦略も読み取れます。まずDFP-10917は前述の通り米FDAからオーファンドラッグ指定を受けており、承認取得に向けた優遇措置(審査手数料免除や支援プログラム利用など)を享受しています。また、FDAとは治験プロトコルに関しても綿密にやり取りしており、VEN併用試験のIND申請も迅速に許可されました。COVID禍での治験遅延時にもFDAと相談し施設追加を行うなど、当局との連携は良好です。
一方、日本のPMDA(医薬品医療機器総合機構)とも緊密に協議しています。DFP-14323に関しては、第2相の卓越した成績をもとに一時は条件付き承認を模索しましたが、PMDAから正式な第3相比較試験実施要請を受け入れる形で進めています。DFP-17729についても対面助言を経て第2/3相試験承認に至っており、同社は規制当局の指導に柔軟に対応しつつ開発リスク低減を図っています。
知的財産(IP)の面では、開発品すべてに物質特許や用途特許を取得済みか出願中です。同社の強みとして「全開発品を新規物質として特許化」という点が挙げられている通り、ライフサイクルマネジメントも抜かりありません。DFP-10917単剤については特許出願状況は不明ですが、併用療法(DFP-10917+VEN)特許を米日台で取得済み(2040年まで有効)。DFP-14323は日米欧ほか主要国で単剤および併用の特許を成立させており、2020年には長期安定製剤に関する新規特許もPCT出願して実質的な特許期間延長を図っています。DFP-17729も日本・韓国で特許成立、他のPCT加盟国でも審査中です。さらに、同社は2025年4月にDFP-10917の凍結乾燥製剤に関する新しい特許をPCT出願し、仮に単剤本体の基本特許が承認前に期限を迎えても製剤特許で独占権を延長できるよう備えました。このように、多角的に知財を確保することで、承認取得後の排他期間を最大化し収益を守る戦略です。
なお、デルタフライ社は製造販売自体はパートナー企業に委託・ライセンスアウトする方針ですが、それでも品質管理やCMC(Chemistry, Manufacturing and Controls)には責任を持って取り組んでいます。同社は自社では製造設備を持たないファブレス企業であるため、製造工程は外部CMOに依存します。そのため各種契約で製造物責任に対処すべく十分な保険加入を行うなど、リスクマネジメントも講じています。逆に言えば、自社で大規模工場を持たない分コスト固定費は低く抑えられ、状況に応じて柔軟に製造委託先を選べるメリットもあります。承認取得後は、海外の大手製造受託企業に生産委託しつつ自社が製剤をパートナーに供給することで、ライセンス収入に加えて30~40%程度の製造マージンを得ることも可能とコメントしています。これは一般的なロイヤルティ(売上の10~20%程度)より収益性が高く、パートナー販売+自社製剤供給というビジネスモデルで収益最大化を狙っています。
総じて、デルタフライ社は規制当局対応・知財確保・製造体制構築の各面で周到に準備を進めており、パイプラインの価値を最大化する体制を整えています。これは個人投資家が同社に安心感を持つ材料でもあり、今後承認審査段階に入った際には、これらの下地がスムーズな承認取得・市場導入につながると期待されます。
見込まれる医薬品市場規模と収益インパクト
米国における急性骨髄性白血病(AML)の治療ライン別患者数の概念図。同社試算では、難治性・再発AML領域の潜在治療患者数は全米で約20,000人、実際に治療対象となり得る患者数は約10,000人規模とされています
DFP-10917はこの第3次治療以降の救援療法に位置づけられており、同領域には有効な治療法が限られることから、承認されれば重要な治療選択肢となる可能性が高いといえます。
デルタフライ・ファーマの開発品がターゲットとする市場は、いずれも一定規模以上の医療ニーズが存在します。まずDFP-10917(AML向け)について、AMLは希少疾患ではありますが再発・難治患者に対する有効薬が乏しく、市場性は決して小さくありません。同社の推計では、ベネトクラクス併用療法まで含め治療領域が拡大した場合、全世界の市場規模は1,800億円、ピーク時年間売上高は800億円程度になると見ています。これはDFP-10917が標準治療の一角として定着したケースを想定した数字で、さらに初発治療(1次治療)でも併用使用されるようになれば売上高は数倍にもなり得るとされています。仮に世界で800億円規模の年商を上げれば、デルタフライ社が受け取るロイヤリティ収入だけでも10~20%として80~160億円/年、製剤供給利益も合わせればそれ以上の売上が期待できます。これは現在の同社規模から考えれば桁違いの収益インパクトであり、まさにゲームチェンジャーとなり得るポテンシャルです。
一方、DFP-14323(NSCLC向け)が対象とする肺がん市場は、AML以上に巨大です。非小細胞肺がんは罹患数・死亡数ともに世界トップクラスのがんであり、EGFR遺伝子変異陽性というサブタイプに限っても、日本で潜在治療患者数約3.2万人(EGFR変異陽性の肺腺がん患者)との推計があります。DFP-14323は当初この高齢・脳転移を伴う患者層に照準を当てていますが、国内独占販売契約先である日本ケミファの試算によれば、国内だけで年間100億円規模のピーク売上が見込まれるとの観測もあります(契約一時金やマイルストーン総額の大きさから逆算した市場期待)。実際、DFP-14323の第2相通過時には時価総額が70億円から100億円へ上昇した経緯があり、市場はその将来価値を徐々に織り込みつつあります。さらに、第3相試験が成功すればNSCLC治療ガイドラインへの掲載や標準治療化も期待され、国内外への適応拡大・海外提携によるグローバル展開が現実味を帯びます。NSCLC全体の市場規模は数兆円にも達するため、仮にDFP-14323が一部でもシェアを獲得すれば、それだけで同社の企業価値が何倍にも跳ね上がる可能性があります。
DFP-17729(膵臓がん向け)は、患者数自体は比較的限られる領域です。膵臓がんの年間罹患数は日本で4万人弱ですが、そのうちステージIV末期で既存治療が効かない患者となると数千人規模と推定されます。それでも、現状で有効な治療法が乏しいため、ニーズは深刻です。デルタフライ社は日本ケミファとの契約条件から逆算し、本剤の国内ピーク売上を数十億円規模と見積もっている可能性があります(例えば50億円/年程度)。単剤売上は上記2品目ほど巨大ではないものの、DFP-17729は免疫療法増強剤として他がん種にも応用し得る点や、併用するTS-1などがん治療薬自体の市場がある点を考慮すれば、将来的な売上潜在性はさらに上振れ余地があります。また、本剤についても日本ケミファから契約一時金1億円+マイルストーン収入が既に支払われており、販売時にはロイヤリティが入る契約です。パートナー企業のコミットメントを見る限り、少なくとも日本国内市場において早期黒字化に貢献できる製品になることが期待されます。
デルタフライ社全体で見れば、将来的な収益源はライセンス収入(契約一時金・マイルストーン)+ロイヤリティ+製剤供給収入となります。ロイヤリティ率は一般に売上高の数%台後半~20%程度ですが、前述のように製造供給を絡めて実質的な粗利率向上を図る戦略です。加えて、抗がん剤は承認取得後は競合が少ない場合短期間で市場浸透しやすく、高利益率を維持できる傾向があります。同社自身も「承認されると普及が早い」「代替品がない領域では利益率が高い」とコメントしており、複数品目が上市すれば高収益体質への転換が期待できます。
現状の株式市場で評価される同社の時価総額は約75~80億円前後(株価約700円×発行株数約1,092万株※2025年6月末時点)に過ぎません。これはまだ製品売上のない創薬ベンチャーとしては致し方ない水準ですが、上記のように一つでも製品化に成功すれば企業価値が飛躍的に向上する可能性があります。例えば、DFP-10917のピーク売上800億円のシナリオでは、その数割が同社の取り分となりますから、年間100億円以上の利益をもたらし得ます。その場合、製薬企業のバリュエーションで数百億~千億円規模の時価総額がついても不思議ではありません。事実、過去の国産バイオベンチャーでも「時価総額数十億円→数百億円以上」への急騰例は多数あり、サンバイオなど一時時価総額6,000億円超に達したケースすら存在しました。もちろん、それらの中には治験失敗で急落した例もありますが、デルタフライ社の場合は複数パイプラインで成功のチャンスがある点がリスク分散となっています。
各種メディア・コミュニティでの注目度と世論動向
デルタフライ・ファーマは、個人投資家の間で近年注目度が急上昇している銘柄です。Twitter(X)上では「#デルタフライ」「4598」などのハッシュタグ付きで日々多くの投稿が見られ、材料ニュースや株価急騰・急落時にはトレンド入りすることもあります。とりわけ株式掲示板系アカウントからは、「ワラント(新株予約権)行使による株式供給があっても株価が陽線を保った」「○○円台は安すぎる」といった声が散見され、熱心な個人投資家が多い印象です。株価が大きく動いた日の夜には解説ツイートが飛び交い、翌日の値動きを予想する書き込みが賑わっています。
Yahoo!ファイナンス掲示板でも、その熱気は顕著です。同掲示板では極めて強気な論調が主流で、長期ホルダー達が中心となってポジティブ情報の交換・拡散が行われています。ある投稿者は「古参以外は、デルタの話以外は禁止。売り煽りや懸念点なんて書こうものなら村八分にされる」という冗談交じりのコメントを残しており、良い話以外は受け付けないムードさえあるといいます。それほどまでに同社への期待が高く、「買い煽り」とも取れる強気発言が多いのが特徴です。
もっとも、一部では過度な楽観に対する警鐘も鳴らされています。匿名掲示板の5ちゃんねるなどでは、「データカットオフが予定より遅れて6月中に来なかったら暴落だね。約束を守れない会社に大型提携なんて無理」という辛辣な意見も見られました。株価急騰後には利食い優先の短期トレーダーも参戦し、値動きが乱高下する局面もあったため、「信用残が増えたら振るい落としが来るだろうけど、それでもこの時価総額は安すぎる」とボラティリティを織り込んでも強気を崩さない投資家もいます。このように、楽観派と慎重派が入り混じりつつも、総じて「デルタフライ株は将来大化けする可能性がある」との見方が大勢を占めています。
注目すべきは、コミュニティ内での情報共有と士気向上の動きです。Yahoo掲示板では有志が過去のIR資料や論文を引っ張り出して解説したり、5chでは「盛り上がってるなで入る人は調べない。調べる人はもう仕込んでる。古参が単剤、併用、他パイプラインを教えて新規ホルダーを育てねば」といった書き込みがありました。これは、新規参入組にパイプラインの価値を説き、短期売買ではなく長期ホールドを促す内容で、まるで布教活動のようです。実際、「20円抜きで逃げる新規を治験結果まで握力ゴリラに成長させるのが古参の利益に繋がる!」とのユーモア交じりの表現もあり、古参ホルダーたちは株価上昇のため結束している様子が伺えます。
また、株式専門メディアやブログでも注目度は高まっています。株探やトレーダーズウェブなどでは、デルタフライに関するIRニュースが出る度に「ストップ高」「買い気配」といった見出しで取り上げられます。例として、2024年9月にDFP-10917+VEN併用試験の症例登録開始を発表した際には、翌営業日に株価が買い気配スタートとなり話題になりました。ニュース記事でも「新薬の実用化と大手製薬との契約締結期待の買い」と解説され、IR一つで株価が数割動くボラティリティも相まって、市場の注目材料銘柄となっています。
海外の投資家コミュニティではまだ知名度は限定的ですが、米国のバイオ関連掲示板ではFDAのオーファン指定や臨床試験情報が断片的に共有されています。今後、もし米国でDFP-10917の承認申請が具体化すれば、海外投資家からも注目される可能性が高いでしょう。同社は2023年6月の米バイオ国際会議(BIO International Convention)にも参加しライセンス交渉を行ったとIR開示しており、国際的なプレゼンス向上にも努めています。
株価の見通しと専門家・市場参加者の声
デルタフライ・ファーマの株価見通しについて、専門家や市場参加者からは総じて明るい将来予測が語られています。ただし、それは「各開発品が順調に成功すれば」という前提付きであり、ハイリスク・ハイリターンである点も認識されています。
アナリストレポート等では、「デルタフライ社のパイプラインは大型製薬に匹敵する収益規模の可能性がある」と評価されています。特にDFP-10917の年間700億円という販売予測は業界内でも注目され、「国内バイオベンチャーの中でも群を抜くポテンシャル」との声もあります。Shared Researchレポートでも、デルタフライ社の開発品群は国内大手10社をも凌ぐ研究開発費比率で投資されており、その果実が近づいている点が強調されています。同レポートは前述の強み・弱み分析を踏まえ、「短期間・低コスト開発の優位性を活かし、新薬承認とライセンス契約による収益化を着実に狙える」として、中長期的な成長余力に太鼓判を押しています。
市場参加者の声としては、「まずDFP-10917の結果待ち」という意見が大多数です。掲示板などでも「今はOSフォローアップ中だが、このデータが出てきたらかなり高い確度で(株価が)上がってくると思っている」とのコメントがあり、経営陣自身も「OSデータが出れば高い確度で(ライセンス交渉が)上がってくる」と発言しています。これは2023年の決算説明会での社長回答とみられますが、要するに「データ次第で大型提携がほぼ決まる」とのニュアンスで、市場もそれを期待してスタンバイしている状況です。
専門誌や投資顧問筋からは、「承認取得時の企業価値を逆算すると現在株価には大きな割安感がある」との指摘も出ています。類似企業のケーススタディでは、治験成功・承認取得に至ったバイオ株の株価数十倍化は決して珍しくなく、デルタフライも例外ではないという見方です。一部の強気な個人投資家は「時価総額1,000億円超えも視野」などと豪語していますが、これはさすがに楽観的すぎるとしても、現状の時価総額80億円前後が低評価であることは多くの投資家が同意するところでしょう。
実際、証券会社の企業評価モデルでは、DFP-10917単体でもNPV(現在価値)で数百億円規模に達する可能性があります。例えばピーク時売上800億円・成功確率50%・ディスカウント率10%で試算すると、ざっくりNPV200~300億円となり、現在の時価総額の数倍に相当します。そこに他のパイプラインのオプション価値を加味すれば、「成功期待値」としての株価上昇余地は大きいと考えられます。もっとも、創薬株特有のリスク(治験失敗、承認遅延など)もあるため、専門家は「投資は余裕資金で、リスク許容度と相談しながら」と注意喚起も行っています。
総括すると、デルタフライ・ファーマは個人投資家にとって夢のある銘柄です。モジュール創薬というユニークな手法から生み出されたパイプラインは、臨床試験で着実に成果を挙げつつあり、いくつかは既に提携先もついています。専門家や市場関係者の評価も「もし成功すれば凄いことになる」という点で一致しており、現時点では成功確率の見極めこそ難しいものの、将来の大化け候補として期待されていることは間違いありません。今後1~2年で控えるDFP-10917の治験結果やFDA申請、DFP-14323・17729の後期試験進捗など、マイルストーンが相次ぐ予定であり、ポジティブなニュースが出る度に株価のステージが引き上がっていく可能性があります。個人投資家にとってはリスク管理が必要な銘柄ではありますが、「国産創薬ベンチャーの星」として大化けするシナリオを信じ、熱い視線を送り続ける価値がある銘柄と言えるでしょう。
未上場会社 株式会社コーンテックへ出資。上場まで応援します